2022年4月1日の改正道路交通法施行規則の施行に伴い、所定の要件を満たす事業所の白ナンバー車両でもアルコールチェックが義務化され、さらに2023年12月からはアルコール検知器を使用した酒気帯び確認も必須となっています。
飲酒運転による悲惨な事故を防ぐ目的のために義務化されたアルコールチェックですが、残念ながら「アルコール検知器の検査をごまかす」といった不正行為を試みる人もいます。
飲酒運転は悲惨な事故を引き起こす可能性のある危険行為で決して許されません。
そんな飲酒運転を防ぐためにはアルコールチェックの徹底と不正行為の防止が不可欠です。
本記事では、アルコール検知器を利用した検査の重要性や、よくある不正行為の実例、そして企業が取り組むべき防止策について解説します。
ぜひ参考にして、飲酒運転とそれによって引き起こされる事故を防ぎましょう。
アルコールチェックを行う重要性
飲酒運転が原因の悲惨な事故によって多くの方が体だけではなく、心にまで深い傷を負ってきました。
車両を使用する事業者にとって、運転者が飲酒をしていないかを確認するアルコールチェックはとても重要なものとなります。
この章ではアルコールチェックをすることで、具体的に防ぐことができる事柄を見ていきましょう。
交通事故防止
1つ目は、飲酒運転によって起こる交通事故です。乗車前にアルコールチェックを常に行うことで、飲酒運転による悲惨な事故を予防できるようになります。
さらに業務の中にチェックを取り入れることで「飲酒運転はしてはいけないこと」「安全に運転しなくてはいけない」ということを改めて従業員に意識させるきっかけにもなります。
法的義務・罰則
2つ目に、法的義務を守ることで罰則を受けるような事態を防ぐことができます。
詳しく見ていきましょう。
アルコールチェックに関する法的義務
道路交通法施行規則の改正により2022年4月以降、貨物自動車運送事業や旅客自動車運送事業などに用いられるいわゆる「緑ナンバー」車両だけでなく、それまで義務化されていなかった営業車などの「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者にも、アルコールチェックが義務化されました。
また2023年12月1日からは、自動車運送事業者と同様に、上記アルコールチェックの際にアルコール検知器を使用することが義務づけられています。
これらの義務は、直接的には該当する事業者が選任する安全運転管理者の義務として位置づけられています。
安全運転管理者とは、自動車の安全な運行に必要な業務を担う存在です。
一定台数以上の自動車を使用する企業は、事業所ごとに安全運転管理者の選任を行わなくてはいけません。
道路交通法施行規則の改正に伴い、安全運転管理者の業務として、以下の事項が加わることとなりました。
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより酒気帯びの有無をチェックする
- 運転者の酒気帯びに関する検査結果を記録し、記録を1年間保管する
(2022年4月1日施行) - 運転者の酒気帯びの確認をアルコール検知器を使って行う
- アルコール検知器を常時有効に保持する
(2023年12月1日施行)
2022年4月に施行された改正では目視で酒気帯びの有無をチェックすることのみが必要とされていましたが、2023年12月からはアルコール検知器を使用しての確認が義務となりました。
アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに当てはまり安全運転管理者の選任を要する事業所です。
- 乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上使用する事業所
- 白ナンバー車を5台以上使用する事業所
※オートバイは0.5台として換算
アルコールチェック義務を怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠ることは、安全運転管理者の業務違反です。
業務違反と聞くと何らかのペナルティが科されるのでは?と思う人もいるでしょう。
業務違反をしたからと言って安全運転管理者や事業者が直接的な罰則の対象となることはありません。
しかし公安委員会によって安全運転管理者の解任を命じられる可能性がありますし、罰則が仮にないとしてもアルコールチェックを怠ることはしてはいけません。
運転者が飲酒運転をした場合の罰則
飲酒運転をした場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」違反となります。
この場合、運転者だけでなく、代表者や安全運転管理者などの責任者も、最大で5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また運転者が飲酒した状態であることを認識しつつ、運転を命じていた場合などにも、運転者に加え運転を命じた者も刑事責任を問われることがあります。
アルコールチェック義務化の対応方法と実施のポイント【弁護士監修】
道路交通法施行規則が改正され、現在は緑ナンバーだけでなく、一定台数以上の白ナンバーの社用車を持つ事業者にも安全運転管理者の選任とアルコールチェックの実施と記録の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェックが義務となる事業者と対応方法、実施のポイントについて紹介しています。
ごまかすことはできる?アルコールチェックの不正行為とは
飲酒した本人は、アルコールチェックを受ければ自分からアルコールが検出されることを分かっています。
そのため、許されないことではありますが「どうにかごまかせないか」と考える人もいるようです。
この章では、アルコールチェックの不正を見逃さないためにも具体的にどのような不正があるのかご紹介します。
他人の息を吹きかける
「他人の息を吹きかけるって、どういうこと?」と思われるかもしれません。
出張や直行直帰をする場合、誰がアルコールチェックを受けたか、直接確認することはできません。
例えば、同乗者が飲酒をした本人に代わってチェックを受けるという不正を働く人がいる可能性もあるのです。
これは飲酒した人だけでなく、不正に協力した同乗者にも不正をすることの危険性などを指導する必要があります。
吐ききった後の弱い息を吹きかける
息をすべて吐ききった後、残った少量の息だけをアルコール検知器に吹きかけるという不正行為があります。見た目はしっかりと検査に応じているように見えるものの、実際には検知器が反応しないごくわずかな息しか吹きかけておらず、飲酒の事実を隠す悪質な手口です。一見、正しくチェックを受けているように見えるため、この不正を見つけることは難しいでしょう。
そのためアルコール検知器の使用を対象者自身に任せるのではなく、常に責任を持って安全運転管理者が行うようにしましょう。その際、対象者が不審な動きをしていないかも含めて確認することをおすすめします。
ポンプなどの道具を用いて検査する
アルコール検知器に息を直接吹きかけず、代わりにポンプなどの道具を使用するという不正もあるようです。これにより、他人の息を吹きかけるのと同様に、アルコールを含まない空気で検査をすり抜けてしまいます。
アルコールチェックの際は、何か小道具を持っていないか、異常に周囲を警戒していないかなどおかしな行動をしていないかを注意深く観察するようにしましょう。
食べたものなどを言い訳にする
アルコールを摂取していなくても、アルコール検知器がエタノールやアルコールを含む食品や製品に反応するということがあります。
具体的には、パンやキムチなどの発酵食品やマウスウォッシュなどの口内洗浄剤、そしてエナジードリンクなどに反応してしまうことがあります。
製品に含まれるアルコール成分により、検知器が誤って反応することがあることを知っている運転者は、そのことを利用して検知器に反応した際に「アルコール成分を含む食品を直前に摂取しただけ」などと言い訳をして、飲酒した事実をごまかそうとする場合もあるようです。
飲酒していないのにアルコールチェッカーが反応する原因は?対応策も徹底解説します!
飲酒運転による事故を防ぐため、2023年12月からアルコールチェッカーを使用したアルコールチェックが義務化となった。そんな中、お酒を飲んでいなくてもアルコールチェッカーが反応するケースも報告されているが、アルコールチェッカーの誤検知はなぜ起こるのだろうか。今回は、アルコールチェッカーが誤検知する原因や対策について、詳しく解説します。
今回紹介した不正行為の中には「こんなことできるの?」と思ったものもあるかもしれません。
不正を行おうとも思わない方にとっては、驚くことも多いでしょう。
しかし、どうにかして不正を防ぐためには、思い込みを取り払い柔軟な思考で向き合うことが大切です。事前に不正行為の可能性を認識し、それに対応する対策を講じることで、より安全な管理体制を整えましょう。

不正防止と業務負担を軽減!アルコールチェック検知器と連携オプション
アルコールチェックを適切に行うための方法
ここまでアルコールチェックの重要性や具体的な不正行為についてお話ししてきました。
この章では、正しくアルコールチェックを行う方法を見ていきましょう。
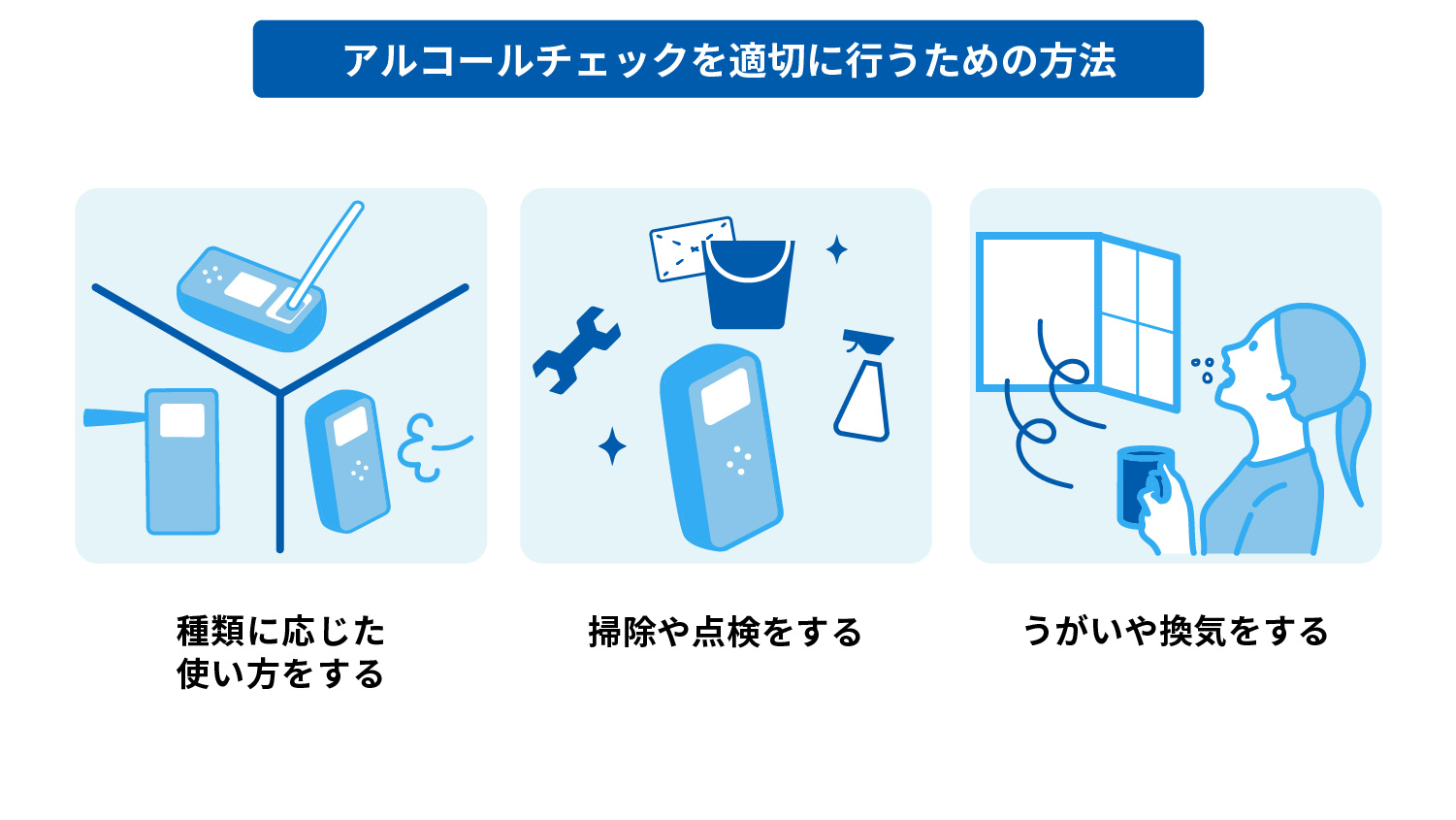
アルコールチェッカーの種類に応じた使い方をする
アルコールチェッカーの種類は、大きく3つあります。
ただしくアルコールをチェックするためには、それぞれのタイプに応じた使い方をすることが大切です。
それぞれの測定方法を紹介します。
1つ目はマウスピースタイプです。
専用のマウスピースを使用した上で息を吹き込むことで検査します。周囲の空気の影響を受けにくく、検査の精度が高いとされています。
2つ目は吹きかけタイプです。
機器本体に直接息を吹きかけることで、飲酒したかどうかを測定します。
3つ目はストロータイプです。
ストローを機器に差し込み、口に咥えて息を吹き込むことでアルコール値を測定します。息が直接機器に届くため、吹きかけタイプよりも精度が高いとされています。
このことから正しく検査をしたいならマウスピースタイプもしくはストロータイプのアルコール検知器を選ぶと良いでしょう。
アルコールチェッカーの掃除や点検をする
アルコールチェックを行う前に、アルコール検知器が正常に動作しているかを必ず確認してください。電源がちゃんと入るか、機器に損傷や不具合がないかを確かめましょう。
確認が終われば、正常な呼気で実際に検査を行い、誤った結果が出ないかをチェックします。その際、同じ条件で何度か検査を行っておきましょう。何度試しても同じ結果が得られるか、それとも検査ごとに異なる結果がでるのかを確認することで正しく飲酒しているかを検査できます。
アルコール検知器は使用すればするほど劣化します。正確な検査を続けるために、定期的なメンテナンスやクリーニングが必要です。
いかなるときでも、アルコールチェッカーが正常に作動するように努めることも、安全運転管理者の義務の1つと言えます。機器の状態を常に最良の状態に保ち、確実な検査ができるように、こまめに手入れを行いましょう。
うがいや換気をする
口内に食べ物や飲み物の成分が残っていると、アルコール検知器が誤反応を示すことがあります。
例えば、飴やガムに含まれる清涼剤、プリンやキャラメルの香料など、アルコール成分とは関係がなくても検知されやすい傾向にあるようです。そのため、アルコールチェックを行う前には、必ずうがいや水で口をすすぎ、口内に残った成分を洗い流したり、室内を換気するようにしましょう。
また、検査前に飲食物の摂取を控えるよう注意を促すことも効果的です。
アルコールチェック記録簿の基本とテンプレート紹介
アルコールチェック記録簿は、法定の項目を記載の上、1年間の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェック義務化の内容と背景、その重要性とアルコールチェック記録簿の作成方法、テンプレートを紹介しています。
アルコールチェックの不正を防ぐために企業ができる対策
様々な不正が行われている中、企業はどのように不正を未然に食い止めればいいのでしょうか。
具体的な対策を4つご紹介いたします。
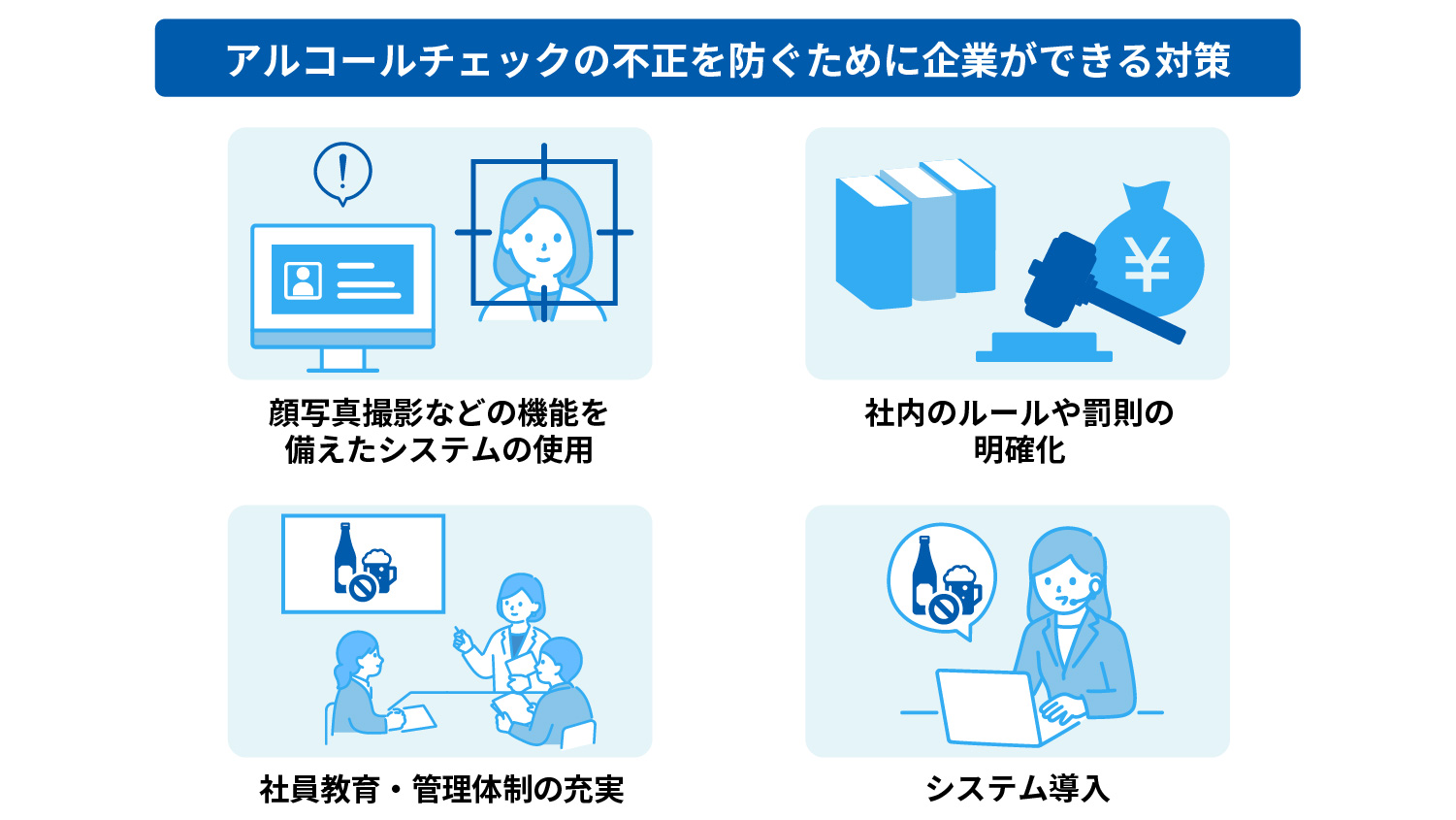
顔写真撮影などの機能を備えた検知器やシステムの使用
アルコールチェックの不正行為は、目の前で検査を実施しているかを確認できれば防げるものもあるでしょう。しかし、多くの業務を抱えている管理者が毎回チェックの場に同席できる訳ではありません。
そのため、測定時の様子やチェックを受けている人物の顔写真を撮影するなどの機能を備えた探知機もしくはシステムを使用すると良いでしょう。
仮に管理者が直接確認できない状況であっても、顔写真を撮影することで他人がなりすまして検知することを防ぐことができます。
アルコール検知器は、据置型と運転者に携行させる携帯型があります。
据置型
| 使用可能な場所 | 事業所など安定して探知機を置いておけるスペースが確保できる場所 |
|---|---|
| 不正防止策 | カメラを設置して、アルコールチェックの様子が把握できるアングルで撮影・記録する、またはシステムによっては、PCカメラと連携させて静止画が残せる機能があるのでなりすましを防ぐことができます。 |
携帯型
| 使用可能な場所 | 事業所と車庫間でも使用することができます。 そのため出張時や直行直帰の場合でも使用可能です。 |
|---|---|
| 不正防止策 | 携帯電話などに備わっているカメラ機能で測定時の様子を撮影。撮影した写真を管理者に送信することで不正を防ぎます。 ただ本人が撮影するため、不正をさせないルールを設ける必要がある場合もあります。 |
安全運転管理者には、酒気帯び確認内容の記録・保存が義務付けられています。アルコール測定時の様子は記録としてしっかり残しましょう。
社内のルールや罰則の明確化
アルコールチェックに関するルールや検査に必要な手順を明確にしましょう。従業員が誤った方法で検査を受けている場合もあるかもしれません。
アルコールチェックを行わない、誤った方法で検査を受けることに関して罰則はありません。ただ安全運転をし続けるためには、必ず受けなくてはいけない重要な検査です。
どういう手順でアルコールチェックを受けるかを社内全体で理解しておくことが不正を防ぐことにつながります。
また、合わせて飲酒運転に関する罰則についても伝え「不正は絶対にしてはいけない」と認識させることも重要です。
社員教育の実施や管理体制の構築
「飲酒運転は絶対にしてはいけない」ということは、世の中の常識です。
しかし実際には二日酔いの状態で運転してしまったり、時間が経ったから大丈夫だと勘違いして運転してしまったりというケースも見られます。
運転者が自身が飲酒した時間や飲酒した量を正確に把握せず、翌日そのまま業務に従事することは非常に危険です。重大事故や死亡事故を起こすリスクを減らすために、運転者には飲酒の影響について定期的に教育を行うことが必要です。
また、就業規則に飲酒に関するルールを明記し、定期的に全従業員に周知させることで、飲酒運転防止の意識を根づかせましょう。
アルコールチェックに対応するシステム導入
アルコール検知器と連動するチェックシステムやクラウドベースの管理ツールなどのソリューションを併用することで、安全運転管理者の業務負担を大幅に軽減することができます。これにより、測定から記録までのプロセスがスムーズに進行し、管理体制の強化にもつながります。特に規模の大きい事業所では、こうしたツールを導入することが効率向上の鍵となりますので、導入を検討することをおすすめします。
MIMAMO DRIVEでアルコールチェック記録業務を効率化!
MIMAMO DRIVEとは
MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。
MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。
「月報・日報を書く時間がない」
「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」
「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」
そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。
ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。
東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。
MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。
アルコールチェックの記録にMIMAMO DRIVEを導入するメリット
MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。
- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化
- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮
- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化
- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上
- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止
上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。
導入事例
乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を保有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。
リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。
ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。
また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。
- MIMAMO DRIVE 資料紹介
-


MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。
まとめ
今回は、アルコールチェックの重要性や不正行為、正しく検査するための方法についてお話ししました。
いくら安全運転管理者が、飲酒運転を防ごうとしても、どうしても時間や仕事の兼ね合いで時間を割くことができない場合もあります。
もし、安全運転管理者の負担を減らしつつも、飲酒運転を無くしたい企業は、MIMAMO DRIVEの導入をご検討ください。






