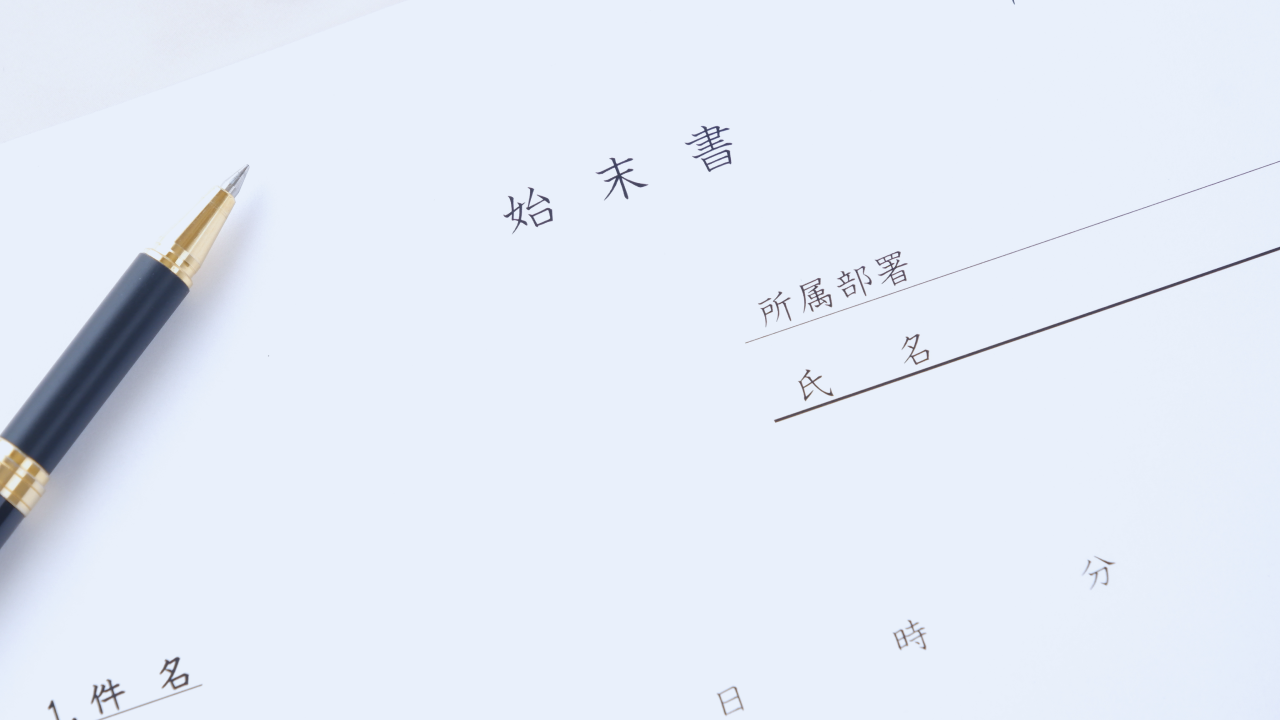始末書とは?目的と反省文との違い
始末書の定義と役割
始末書とは、業務中に発生した事故や破損、規則違反などの事実経過・原因・再発防止策を文書として正式に記録するための社内文書です。
提出先は通常、直属の上司や人事部、総務部などで、社内規定に従って作成・提出します。
多くの企業では、始末書は以下のような役割を果たします。
- 事実の記録:いつ、どこで、何が起きたかを客観的に残す
- 責任の明確化:誰が、どのような行動・判断で事態が発生したかを示す
- 再発防止策の提示:同じ事態を防ぐための具体的な行動計画を明記
- 組織の信頼維持:事故や破損の発生時でも迅速・誠実に対応している証拠として残す
重要なのは、始末書は単なる「お詫び文」ではないという点です。
単に謝罪の気持ちを表すだけでなく、事実・原因・対策というビジネス文書としての機能を持っています。
始末書が求められる背景
始末書の提出は、単なる不注意や軽微なトラブルだけで求められるものではありません。
会社の信頼や法的責任が関わる場面では、後日の説明や対応のために、事実を正式な書面として残す必要があります。
こうした提出が求められる背景には、次のような理由があります。
- 社内外への説明責任:取引先や顧客への説明・対応に備え、事実経過を明確に記録する必要がある
- 法的リスク管理:人身事故や物損事故など、訴訟や保険請求の可能性がある場合に備える
- 内部統制:再発防止のために原因と対策を公式文書として残す
- 社内規定遵守:一定以上の過失や損害発生時に、始末書提出を義務づける社内ルールがある
反省文との違い
始末書と反省文は似た性質を持っています。どちらも過ちに対して反省の気持ちと、謝罪が含まれる文書だからです。
しかし、謝罪の対象や過ちの大きさに違いがあります。
- 始末書は、会社全体に迷惑をかけたり、組織の信頼を損なうような過ちがあった場合に作成するのが一般的です。提出先も上司や人事部など、会社組織に対して正式に出すケースがほとんどです。
- 反省文は、特定の上司や担当者など、個人に対して謝罪の意思を伝えるケースで使われることが多い文書です。比較的軽微な過ちや態度面での問題など、組織全体に大きな影響を与えない場合に作成されます。
厳密な法律上の定義があるわけではありませんが、一般的には
- 始末書=「組織に対する正式な謝罪文」
- 反省文=「特定の人に対する謝罪文」
と理解しておくとよいでしょう。
| 始末書 | 反省文 | |
|---|---|---|
| 目的 | ・ミスやトラブルの経緯報告 ・謝罪と反省の意を表明する |
・謝罪と反省の意を表明する |
| 記載内容 | ・ミスやトラブルの経緯と原因 ・対応状況 ・謝罪や反省の内容 |
・謝罪や反省の内容 |
| 作成者 | ・ミスやトラブルの当事者 | ・ミスやトラブルの当事者 |
| 提出先 | ・直属上司 | ・上司/謝罪相手 |
また、混同されやすい文書として顛末書があります。顛末書は謝罪や反省を目的としたものではなく、トラブル発生の経緯や事実関係を正しく共有するための報告文書です。顛末書は「事実を客観的に記録する」ことを目的としています。
始末書に必要な3つの要素
始末書は、「感情」よりも「事実と改善策」を重視します。最低限、以下の3つが欠かせません。
-
事実経過
- いつ、どこで、何が起きたのか
- 誰が関わったのか
- 損害や影響の具体的内容
-
原因の分析
- 自分の行動や判断のどこに問題があったか
- 外的要因があっても、自身の責任部分を明確にする
-
再発防止策
- 具体的かつ実行可能な改善策を提示
- ルール改定や確認体制の強化など組織的対策も含める
この章では、始末書の意味と反省文との違い、そして求められる背景と意義を整理しました。
次章からは、具体的に「どんな場面で始末書が必要になるのか」を事故・破損の種類別に解説していきます。
交通事故で始末書が必要になる主なケース
交通事故が発生した際、状況や影響の大きさによっては会社から始末書の提出を求められることがあります。
ここでは、交通事故に関連して始末書が必要となる代表的なケースを整理します。
人身事故
- 概要:歩行者や他のドライバーにケガを負わせてしまった場合。
- 記載ポイント:事故の日時・場所・相手方の状況、応急処置や警察対応の有無を正確に記録。
物損事故
- 概要:他人の車や建物、施設、ガードレールなどを損傷した場合。
- 記載ポイント:破損箇所や修理の有無を記載し、原因と再発防止策を具体的に示す。
軽微な接触事故
- 概要:駐車場や狭い道路で、他車や構造物に擦ったり軽くぶつけたりした場合。
- 記載ポイント:接触状況を客観的に説明し、「距離感の誤認」「ミラー確認不足」など原因を明示。
会社車両の破損
- 概要:単独事故で自社の社用車を破損させた場合(例:縁石に乗り上げてバンパーを破損)。
- 記載ポイント:運転状況、確認不足や操作ミスの具体的内容を明確に。
速度超過など規則違反による事故
- 概要:スピード違反、一時停止違反など法令違反が伴う事故。
- 記載ポイント:違反内容を隠さず記載し、今後の再発防止策を明示。
事故・破損別 始末書例文集
ここでは、人身事故/物損事故/社用車破損の破損の3つのケースについて、実際に使える始末書の例文を紹介します。
それぞれの事例では、概要 → 原因 → 再発防止策 → 謝罪文の流れを守っています。
状況に合わせて文言を修正し、社内規定に沿ってご利用ください。
交通事故に特化した始末書例文集
人身事故の始末書(歩行者との接触)
宛名:営業部 部長【○○】様
日付:【令和〇年〇月〇日】
氏名:営業部【氏名】
始末書
【令和〇年〇月〇日】【午後〇時〇分】頃、【○○市○○町○丁目 〇〇交差点】において、配送業務中に社用車を運転中、横断歩道を渡っていた歩行者の方と接触し、軽傷を負わせる事故を発生させました。事故直後に車両を安全な場所へ停車し、負傷状況の確認と119番通報を行うとともに、110番通報のうえ警察の現場確認に応じました。
本件の原因は、交差点進入時の安全確認不足および減速の不徹底にあります。信号が青であったことに過度に依拠し、左前方の横断開始者への視認が遅れました。
再発防止策として、①交差点30m手前での減速・左右確認の徹底、②横断歩道付近ではすぐに止まることができる速度で運転(時速10km/h目安)、③出庫前チェックリストに「交差点手前減速・視線移動」を追記し、日々の点検で遵守状況を記録します。また、月次の安全運転教育に参加し、日々の運転の振り返りを行います。
この度は被害者の方ならびに関係各位に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。以後、法令と社内ルールを厳守し、再発防止に全力で取り組みます。
以上
物損事故の始末書(対物:他社設備・他車)
宛名:営業部 部長 【○○】様
日付:【令和〇年〇月〇日】
氏名:営業部 【氏名】
始末書
【令和〇年〇月〇日】【午前/午後〇時〇分】頃、【○○社 ○○物流センター 正門】において、社用車【車種】で後退(バック)の際、右後方の確認が不十分で、門扉に後部バンパーを接触させ、塗装剥離および軽度の変形を生じさせました。直ちに車両を停止し、施設管理者へ報告・謝罪のうえ連絡先を交換、当社総務・保険担当へも連絡しました。また、警備室の指示に従い所轄へ連絡し、指示に従って対応しました。
本件の原因は、後退時のサイドミラー確認の不足にあります。バックミラーを注視しており、車体側面の障害物を考慮せず進行してしまいました。
再発防止策として、①構内での後退速度は3km/h以下を厳守、②後退開始前に一旦停止→バックミラー、サイドミラーの確認、目視確認必ず行います。あわせて、月次の安全運転教育で日々の運転の振り返りを実施します。
この度は施設管理者様ならびに関係各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。損害の修繕・保険手続きは当社手順に従い速やかに進め、上記対策を確実に実施いたします。
以上
社用車破損の始末書(単独:縁石・ポール等)
宛名:総務部 部長 【○○】様
日付:【令和〇年〇月〇日】
氏名:総務部 【氏名】
始末書
【令和〇年〇月〇日】【午前〇時〇分】頃、【○○市○○町 コインパーキング出入口】にて社用車を右折で出庫する際、左後輪が縁石に乗り上げ、バンパー下部の破損を生じさせました。第三者被害はありません。
原因は、出庫時の内輪差の見込み不足と、段差へのアプローチ角の誤りです。出口付近のポール位置と縁石の高さを考慮せず、ハンドル切り始めのタイミングが早過ぎました。
再発防止策として、運転講習会へ参加し、内輪差を意識した運転の徹底ができるよう努めます。また、社内共有用に現場写真と危険ポイント図を作成し、同駐車場利用者へ周知します。
この度は社用車を破損させ、会社に修理費等の負担を生じさせましたことを深くお詫び申し上げます。以後、出庫時の安全行動を厳守し、再発防止に努めます。
以上
提出時の注意点と社内対応のポイント
始末書は書いて終わりではなく、適切な方法で提出し、その後の社内対応まで行うことが重要です。
この章では、提出期限・報告の流れ・メールでの送付方法・確認の仕方など、提出に関する実務的なポイントをまとめます。
提出期限を守る
- 始末書は多くの場合、「事故や破損発生日から◯日以内に提出」と社内規定で定められています。
- 始末書に記載するミスやトラブルの経緯や状況を鮮明に覚えている間に作成することで、より詳しい状況を記載することが可能になります。
- 提出が遅れる場合は、必ず事前に上司へ連絡し、理由と提出予定日を説明しましょう。
メール提出時のポイント
件名例
【始末書提出】営業部 ○○(氏名)
本文例
営業部 ○○です。
添付の通り、始末書を提出いたします。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
営業部 ○○ ○○
内線:1234
添付ファイル名
始末書_営業部_氏名_20250810.pdf
注意点
- 改ざん防止のためPDF形式で送付
- 提出前に添付漏れや誤字脱字を必ず確認
提出後の社内対応
始末書を提出した後は、それで終わりではありません。
再発防止策の実行と、関係者へのフォローアップが求められます。
- 対策の実行:始末書に記載した改善策を必ず履行
- 進捗報告:改善策を実施したら、上司や関係部署へ報告
- 関係者への謝罪:被害者や影響を受けた部署へ直接謝罪や説明を行う
- 記録保管:提出した始末書のコピーを自分でも保管しておく(後日の確認用)
5. NG行動とそのリスク
| 提出期限を守らない | 誠意を疑われ、処分が重くなる可能性 |
|---|---|
| 書面だけで報告を済ませる | 対人関係の悪化、信頼低下 |
| 再発防止策を実行しない | 同じミスの繰り返し |
| 添付ファイルの誤送信 | 情報漏洩のリスク、二次トラブル発生 |
提出時の注意点と社内対応を押さえておくことで、単なる形式的な提出ではなく、誠意と改善の意思を伝えるプロセスになります。
MIMAMO DRIVEで安全運転促進・業務効率化!
MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。
MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。
「月報・日報を書く時間がない」
「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」
「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」
そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。
ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。
東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。
MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。
- MIMAMO DRIVE 資料紹介
-


MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。
まとめ
交通事故の始末書の書き方と注意点は、事実経過・原因・再発防止策を組織へ正式に報告する点にあり、反省文との違いも明確です。この記事では、提出マナーや社内ルールに沿った体裁を解説し、人身事故・物損事故・社用車破損の状況別例文(テンプレート)を掲載しました。さらに、走行データとアルコールチェックを一元管理できるMIMAMO DRIVEを活用すれば、事故の未然防止と事実把握が進み、始末書の作成・報告が正確かつ迅速になります。