ETC2.0とは?概要と特徴
ETC2.0は、高速道路の料金収受システムであるETC(Electronic Toll Collection)の進化版です。料金決済機能だけでなく、高速道路と車載器の双方向通信を活用し、渋滞回避支援・安全運転支援・観光情報提供など、多彩な付加サービスを利用できるのが最大の特徴です。
ETC2.0は「道路と車がつながることで、より安全で快適なドライブを実現する次世代型システム」であり、従来型ETCでは取得できなかった経路情報や交通情報をもとに、利用者への案内や割引適用が可能になります
ETC2.0の基本機能
ETC総合情報ポータルサイトの情報によれば、ETC2.0の車載器はDSRC(専用狭域通信)を使い、高速道路の路側機と車両間で双方向通信を行います。これにより、以下のような機能が実現します。
- 渋滞回避支援:道路上の混雑情報を受信し、最適ルートを案内。
- 安全運転支援:落下物、急カーブ、事故多発地点などの注意喚起。
- 一時退出・再進入:高速道路を一時的に出ても、一定時間内に戻れば料金が継続。
- 圏央道割引:対象区間利用時の通行料金を割引。
- 東海環状自動車道割引:東海環状自動車道の通行料金を割引。
これらの機能は、運転者の利便性と安全性を高めるだけでなく、時間短縮や料金節約にも直結します。
導入の背景
ETC2.0の導入は、国土交通省や高速道路会社が進める「安全で快適な道路交通」の実現を目的としており、交通渋滞の緩和、事故防止、観光促進を狙っています。特に2024年以降は、事業用車両の効率化やドライバーの労働時間短縮など、物流業界における利用価値も高まっています。
従来型ETCとの違い(比較表付き)
ETC2.0と従来型ETCの大きな違いは、「料金決済のみ」か「料金決済+双方向通信による付加サービス」かという点です。
従来型ETCは料金所のバーを自動で開閉し、通行料金をキャッシュレスで支払う仕組みですが、ETC2.0はさらに、走行中の経路情報や交通情報を活用して、運転者へのリアルタイム情報提供や割引制度適用が可能になります
以下は公式情報をもとにした比較表です。
| 項目 | 従来型ETC | ETC2.0 |
|---|---|---|
| 料金決済機能 | 〇 | 〇 |
| 双方向通信 | × | 〇 |
| 渋滞回避支援 | × | 〇 |
| 安全運転支援 | × | 〇 |
| 道の駅一時退出 | × | 〇 |
| 圏央道割引 | × | 〇 |
| 東海環状自動車道割引 | × | 〇 |
| 対応車載器 | ETC専用車載器 | ETC2.0対応車載器 |
機能面での優位性
- 情報提供機能:ETC2.0は経路情報を活用し、走行中に最新の交通情報を受信。
- 料金面の利点:特定区間での割引制度や途中下車時の料金継続が可能。
- 安全支援:急カーブや事故多発地点での注意喚起など、事故予防に直結。
対応車載器の違い
従来型ETC車載器ではETC2.0の機能を利用できません。導入には「ETC2.0対応車載器」への交換が必要です。車載器本体やパッケージには、紫色の「ETC2.0」マークが表示されています(詳細は後述の車載器選びの章で解説)。
ETC2.0の主なメリット(公式機能ベース+利用例)
ETC2.0は、従来型ETCにはなかった渋滞回避支援・安全運転支援・途中下車制度・割引制度など、多彩なメリットを備えています。これらの機能は、高速道路の利用効率を上げるだけでなく、運転者の安心感とコスト削減にも直結します。
以下では、ETC総合情報ポータルサイトで紹介されている主なメリットを、具体的な利用例や数値シナリオとともに解説します。
渋滞回避支援
ETC2.0対応車載器は、高速道路の路側機からリアルタイムの交通情報を受信し、渋滞区間や事故による混雑を避けるルートを案内します。
利用例:首都圏〜仙台間の移動
例えば、東京から仙台へ向かう東北自動車道で、栃木県内に渋滞が発生している場合、ETC2.0は東北道→北関東道→常磐道経由のルートを提案。
このルート変更により、所要時間が短縮され、燃料も節約できます。
物流業界では、日々の時間短縮が複数回積み重なることで、ドライバーの拘束時間削減につながります。
一時退出制度
ETC2.0の大きな特徴のひとつが、「一時退出制度」です。
これは、高速道路を一時的に降りて道の駅で休憩や買い物をした後、一定時間内に再度高速道路へ戻れば、降りなかったものとして料金が継続される制度です。
利用例:観光ドライブ
関越自動車道「道の駅 川場田園プラザ」では、インターチェンジから数分で到着可能。東京から新潟へ向かう途中に立ち寄り、地元の名物パンや地元産の新鮮な野菜や果物を購入後、2時間以内に高速道路へ戻れば、料金はそのまま。
従来型ETCでは一度降りると料金が分割計算され割高になるため、この制度は観光や地域特産品購入の後押しになります。
圏央道割引
圏央道の一部区間では、ETC2.0搭載車が対象となる通行料金の割引制度があります。最大で約20%割引されるケースもあり、長距離移動のコスト削減に有効です。
利用例(大井松田IC ⇔ 相模原IC、約44.9km)
圏央道の大井松田IC〜相模原ICを走行する場合、普通車では通常料金1,500円のところ、ETC2.0を利用すると1,390円に割引され、1回あたり110円お得になります。
軽自動車なら80円、中型車では120円、大型車では170円、特大車では290円の割引となり、物流業務での繰り返し利用により年間数万円単位のコスト削減が可能です。
大井松田 ⇔ 相模原(44.9km)
| 車種 | ETC2.0以外 | ETC2.0 |
|---|---|---|
| 軽 | 1,230 | 1,150 |
| 普通 | 1,500 | 1,390 |
| 中型 | 1,770 | 1,650 |
| 大型 | 2,370 | 2,200 |
| 特大 | 3,840 | 3,550 |
東海環状自動車道割引
東海環状自動車道では、ETC2.0搭載車に割引が適用されます。物流や観光利用で通過するドライバーにとって、コスト削減効果が期待できます。
利用例(土岐南多治見IC ⇔ 関広見IC、約39.0km)
東海環状自動車道の土岐南多治見IC〜関広見ICを走行する場合、普通車では通常料金1,430円のところ、ETC2.0を利用すると1,220円に割引され、1回あたり210円お得になります。
軽自動車なら170円、中型車では250円、大型車では340円、特大車では580円の割引となり、物流業務や頻繁な移動を伴う営業活動で繰り返し利用することで、年間数万円〜数十万円単位のコスト削減が可能です。
土岐南多治見 ⇔ 関広見(39.0km)
| 車種 | ETC2.0以外 | ETC2.0 |
|---|---|---|
| 軽 | 1,180 | 1,010 |
| 普通 | 1,430 | 1,220 |
| 中型 | 1,680 | 1,430 |
| 大型 | 2,250 | 1,910 |
| 特大 | 3,650 | 3,070 |
安全運転支援機能
ETC2.0は安全運転支援機能も備えており、落下物や急カーブ、事故多発地点などの情報をリアルタイムで提供します。
利用例:障害物の注意喚起
監視カメラやパトロール、一般の方々からの通報で収集された障害物情報を、その障害物の手前のITSスポットから提供します。

ドライバーは早めに減速・車線変更ができ、事故を回避可能。物流業務では、このような事故予防が車両損害や納品遅延のリスクを大幅に減らします。
ETC2.0のデメリットと注意点
ETC2.0は多くの利点を持つ一方で、導入前に知っておくべきデメリットや注意点があります。これらを理解せずに導入すると、想定していた割引や機能を活用できない可能性があるため注意が必要です。
車載器交換に伴う導入コスト
ETC2.0の機能を利用するには、ETC2.0対応車載器への交換が必須です。
従来型ETC車載器では利用できず、新規購入または交換には本体価格・取付工賃の費用がかかります。
割引制度・機能の対応エリアが限定的
ETC2.0の割引や一時退出制度は、現状では全国すべての高速道路で利用できるわけではありません。(現在社会実験中)
例えば、圏央道割引の対象区間は圏央道の一部区間のみで、道の駅一時退出制度も対象となるインターチェンジが全国28箇所と限られています。
そのため、事前に自分の利用ルートが対象かどうかを確認しないと、「導入したのに使える場面が少なかった」ということになりかねません。
利用頻度が低い場合はコスト回収が難しい
高速道路の利用頻度が少ない場合、導入費用に対して得られる割引額や時間短縮効果が限定的になることがあります。
例えば、年に数回しか高速道路を使わない場合、導入費用の回収に数年以上かかる可能性があります。
これらのデメリットを理解した上で、利用頻度・走行ルート・車両更新タイミングを考慮して導入を検討することが重要です。
次の章では、具体的な割引制度とその利用条件を詳しく解説します。
ETC2.0の割引制度と利用条件
ETC2.0では、従来型ETCでは受けられない割引制度がいくつか用意されています。これらは利用者のコスト削減に直結しますが、現状では適用には条件や対象区間があるため事前確認が必須です。
以下では、ETC総合情報ポータルサイトに掲載されている主要な割引制度と条件を整理します。
1. 圏央道割引
圏央道の一部区間では、ETC2.0を搭載した車両が対象となり、通行料金が割引されます。
| 対象車両 | ETC2.0車載器搭載車(軽・普通・中型・大型・特大) |
|---|---|
| 対象区間 | 圏央道(茅ヶ崎JCT~海老名JCT、海老名~木更津JCT)、新湘南バイパス(藤沢~茅ヶ崎JCT) |
| 条件 | 対象区間を含む走行でETC2.0を利用 |
実際の割引金額は以下のNEXCO中日本の「高速道路料金・ルート検索 ドライブコンパス」にて確認可能です。
高速道路料金・ルート検索 ドライブコンパスhttps://dc.c-nexco.co.jp/dc/DriveCompass.html
2. 一時退出制度
高速道路走行中に道の駅に立ち寄り、一定時間内に再進入すれば、降りなかったものとして料金計算されます。
| 対象車両 | ETC2.0車載器搭載車 |
|---|---|
| 対象施設 | 指定された道の駅(例:川場田園プラザ、南えちぜん山海里 など) |
| 再進入時間 | 2時間以内.0を利用 |
| 条件 | 指定ICから退出・再進入し、利用時間内に戻ること |
割引を最大限活用するための注意点
-
対象区間の事前確認
圏央道割引や一時退出制度は対象区間・施設が限られています。公式サイトや最新の地図データで確認しましょう。 -
条件時間の厳守
一時退出制度では再進入時間を超えると割引が適用されません。 -
期間限定割引の見逃し防止
高速道路会社のキャンペーン情報は定期的にチェックするとお得です。
ETC2.0対応車載器の選び方
ETC2.0サービスを受けるためには、ETC2.0対応車載器(ETC2.0車載器・GPS付発話型ETC2.0車載器・DSRC車載器)が必要です。また、ETC2.0の高速・大容量通信を活用した図形・画像情報等を活用するにはカーナビとそれに連動するETC2.0車載器が必要です。
1. 対応マークの確認方法
ETC2.0車載器には、以下に示すマークや番号等が表示されており、正規なETC車載器又はETC2.0車載器であることを確認することが可能です。
- 「ETC2.0」のロゴあり
- 「DSRC/ETC」のロゴあり
- 「ETC2.0」「■」マークあり
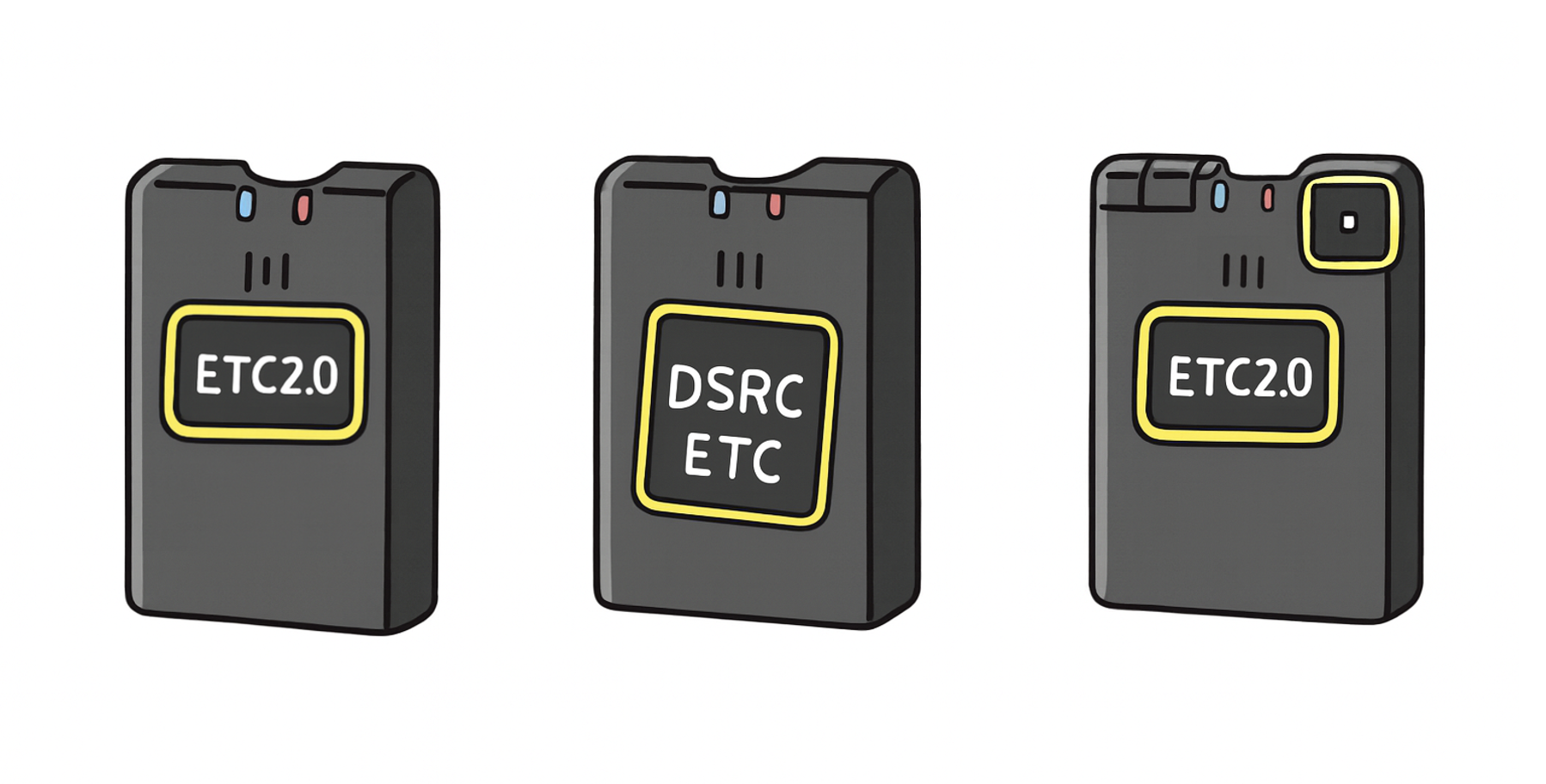
上記の方法で識別できない場合は、購入した販売店またはセットアップ店にご確認下さい。
2. 車載器のタイプ
ETC2.0車載器には、音声案内・アンテナ分離型・2ピース構造など、機能や形状のバリエーションがあります。
選定の際は以下を基準にしましょう。
- 設置場所:ダッシュボード上・グローブボックス内など
- 音声案内の有無:安全運転支援の注意喚起を音声で受け取れるか
- アンテナ形状:一体型は配線が少なく、分離型は設置自由度が高い
3. ナビ連動・スマホ連動機能の有無
ETC2.0の一部機能(渋滞回避支援・経路案内・安全運転支援など)は、カーナビとの連動で活用できます。車載器とナビを有線接続し、ナビ画面上に交通情報や案内を表示。ドライバーは視覚的にルートを確認でき、利便性が高まります。ナビがない場合でも、発話型ETC2.0対応車載器でETC2.0サービスを“音声で”受けることが出来ます。
購入前に、使用中のナビが対応しているか確認しましょう。
4. 購入と取付の流れ
- 対応車載器を選定(公式マークと機能確認)
- 販売店またはオンラインで購入
- 取付予約(ディーラー・カー用品店など)
- 取付後に動作確認(割引制度や案内機能が作動するか)
- MIMAMO DRIVE 資料紹介
-


MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。
まとめ:ETC2.0で安全・快適・お得なドライブを実現
ETC2.0は、単なる料金割引だけでなく、安全運転支援や渋滞回避など、ドライバーに多くのメリットをもたらすシステムです。とくに高速道路を頻繁に利用する方や物流業務を行う事業者にとって、割引効果は年間数万円規模になるケースもあります。
また、車載器の種類によって利用できるサービスが異なるため、導入前には必ず対応状況を確認しましょう。新規導入や買い替えのタイミングでETC2.0を選べば、料金面だけでなく、安全性・快適性の向上も期待できます。
高速道路の利用機会が多い方は、ぜひこの機会にETC2.0の導入を検討し、ドライブや業務の効率化につなげてください。






