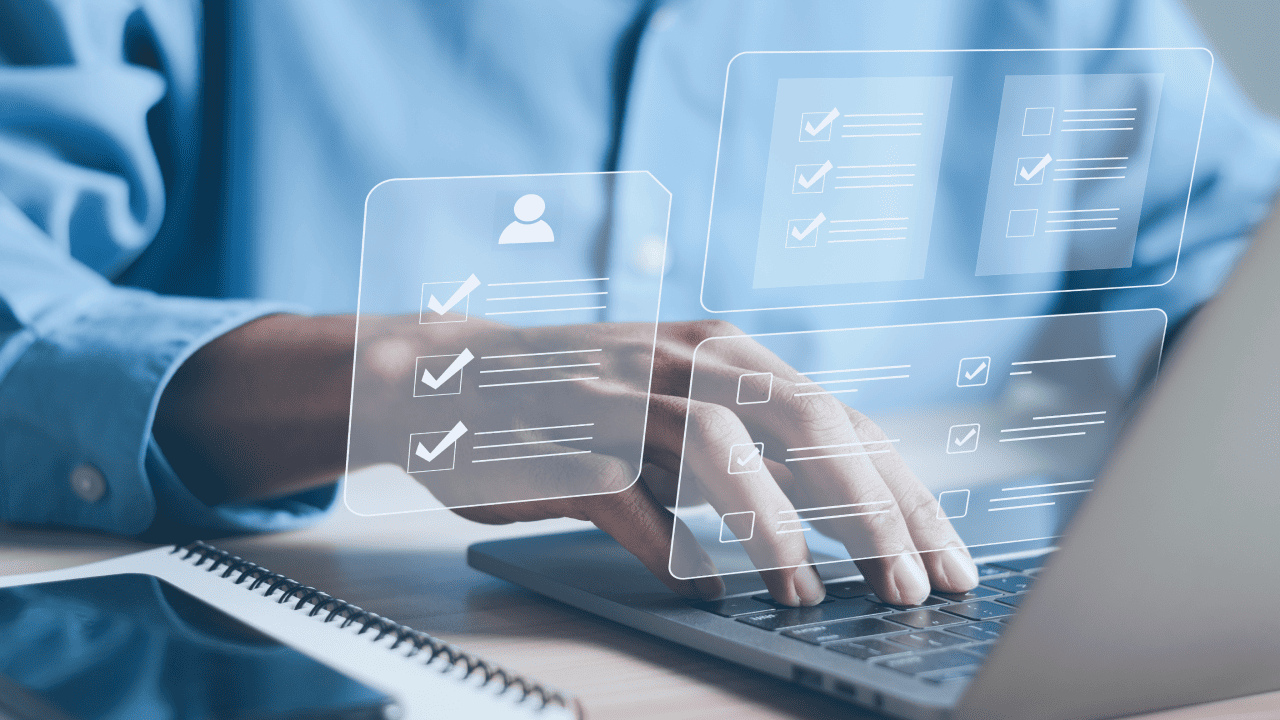建設業は現場仕事が多く、従業員が朝から夜まで現場に出払うことが一般的です。このような環境では、勤務時間や休憩時間の管理が難しく、従業員の自己申告に頼ることが多いです。これにより、企業が気づかぬうちにリスクを抱えてしまう可能性があります。この記事では、建設業における労務管理の課題とその対策について解説します。
建設業の労務管理課題
建設業では、現場が各地に点在しているため、従業員の勤務状況を正確に把握することが難しくなります。タイムカードや日報での管理が難しい場合があり、勤務時間や休憩時間の管理を自己申告としているケースが見られます。
従業員の自己申告に依存することで、従業員の実際の労働時間と申告時間にズレが生じやすく、不適切な給与支払いの原因となることもあります。
不適切な給与支払いにより企業が抱えるリスク
ここでは、不適切な給与支払いにより企業が抱えるリスクと、不適切な給与支払いの発生要因を解説していきます。
(A)給料過払いリスク
給与の過払いリスクは、自己申告の場合に起こり得る問題の一つです。特に自己申告制度に依存している場合、企業が実際の労働時間を正確に把握することが難しくなります。
勤務時間の過大申告のリスク
従業員が実際よりも長く勤務したと申告すると、企業は不必要な給与を支払うことになり、人件費の無駄が発生します。
不適切な休憩時間の申告
休憩時間が適切に管理されていない場合、従業員が休憩を取らずに働いたと申告し、実際よりも長い労働時間を報告する可能性があります。
(B)未払い残業代の発生リスク
未払い残業代が発生すると、企業は法的、財務的、そして社会的なリスクを抱える可能性があります。ここでは、その具体的なリスクについて詳しく説明します。
法的トラブル・追加コストのリスク
未払い残業代が発生すると、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、労働審判の申立てや訴訟の提起を受ける可能性があります。法的手続きに発展した場合、企業には次のような負担が発生します。
人員コストの増加
未払い賃金問題への対応のため担当人員を割かなければならず、本来業務に支障が出ます。
弁護士費用などの負担
訴訟対応には弁護士費用や事実調査のための費用など、追加の出費が必要になります。
法的制裁のリスク
時間外や休日、深夜の労働に対する法定の割増賃金を正しく支払っていない場合、労働基準法代37条違反として民事・刑事・行政上の法的責任を問われる可能性があります。(労働基準法27条)
企業の存続リスク
長期化した法的紛争により、企業経営自体にも深刻なダメージを受ける可能性があります。
また、未払い残業代を後から支払う場合でも、通常の支払い額だけでは済まないケースがあります。例えば、以下のような追加負担が発生する可能性があります。
付加金の発生
使用者が労働者に支払うべき賃金を支払っていない場合に、労働者の請求により、支払うべき賃金に加え裁判所から同一額の付加金の支払いを命ぜられる制裁を受けることがあります。(労働基準法114条)
労働基準法114条
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
遅延損害金の発生
在職中の従業員の場合は、未払い残業代に加え本来の各支払日から年3%の割合で遅延損害金の支払いが必要です。(民法404条2項)
退職した従業員の場合は、賃金(退職手当を除く。)のうちその退職の日(退職の日後に支払い期日が到来する賃金にあっては当該支払い期日)までに支払われなかった賃金の額に年14.6%の遅延利息を支払う必要があります。
こうした追加コストにより、企業の財務負担がさらに増大する恐れがあります。
企業の評判への悪影響
未払い残業代は、企業にとって法的リスクを高めるだけでなく、従業員のモチベーション低下や企業イメージの悪化にも繋がります。
- 求人募集をしても応募者が集まらない
- 既存の従業員のモチベーションが低下し、離職率が上昇する
- 取引先からの信頼を失い、契約打ち切りにつながる
最悪の場合、SNSなどで情報が拡散され、企業経営に影響を及ぼす事態になるかもしれません。
労務管理の適正化に向けた対策
適正化のキーワードは「労働時間の適正な把握」です。
厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しています。(https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001979859.pdf)
実際の労働時間を企業が適切に管理していない実態が長時間労働や割増賃金未払いの問題の一因として捉え、企業の責務を改めて明示するものです。
客観的な記録
労働時間は企業が現認して適正に記録する責務があり、企業はタイムカード、ICカードの記録、パソコンの利用時間など客観的な記録を基礎として労働者の労働日ごとの収支業時刻を確認する必要があります。
時間管理を自己申告で行わざるを得ない場合は、以下の措置を講じることが求められています。
自己申告制の場合に企業が講ずべき措置
- 実態を正しく記録・適正に自己申告することを対象者に十分説明
- 実際に労働時間を管理する者にも⼗分説明
- 把握時間と実際の時間が合致しているか、必要に応じ実態調査を実施・補正(社内にいたデー タと著しい乖離の場合は実施)
- 申告を超える在社理由を報告させる場合、報告が適正かを確認
- 申告できる時間数の上限設定や上限を超える申告を認めないなどの、適正な申告を阻害する 措置を講じないこと
問題になりやすいケースの確認
また当該ガイドラインでは、「建設業の労働時間で問題になりやすいケース」についても詳しく解説されており、従業員の自己申告の場合は特に認識に差異がないかを確認する必要があります。
(A)労働時間の考え方
- 労働基準法における労働時間とは、使⽤者の指揮命令下にある時間のことをいう。使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
- 労働者を必ずしも現実に活動させていなくとも、使⽤者の指揮命令下にある時間であれば労働時間に当たる。
- 労働時間か否かは個別判断であるが、労働時間の考え方そのものは、業種によって異なるものではない。
(B)建設業の労働時間で問題になりやすいケース
| いわゆる「手待時間」 | 使用者の指⽰があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間 (いわゆる「手待時間」)は、労働時間に当たる。 ※例えば、急な需要に備えて⾃宅待機を命じる場合、待機時間の⾃由利⽤が労働者に保障されていないときは労働時間に当たるが、緊急対応の頻度 が少なく、⾃宅待機中に⾷事や⼊浴などの⽇常的な活動や外出をすることが特段規制されていないなど、実質的に使⽤者の指揮命令下にあるとまで はいえないときは、一般的には労働時間に当たらないとされている。 |
|---|---|
| 移動時間 | 直⾏直帰や、移動時間については、移動中に業務の指⽰を受けず、業務に従事することもなく 、移動⼿段の指⽰も受けず、⾃由な利⽤が保障されているような場合には、労働時間に当たらない。 ※例えば、次のような場合は、⼀般的に労働時間に当たるとされている。 ・移動⼿段として、社⽤⾞に乗り合いで現場に向かうこと等が指⽰されている場合・現場に移動する前に会社に集合して資材の積み込みを⾏う場合や、現場から会社に戻った後に道具清掃・資材整理を⾏うことが指⽰されている 場合、移動の⾞中に使⽤者や上司も同乗して打合せが⾏われている場合 |
| 着替え、作業準備等の時間 | 使⽤者の指⽰により、就業を命じられた業務に必要な準備⾏為(着⽤を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した 後始末(清掃等)を事業場内において⾏う時間は、労働時間に当たる。 (労働時間となる例) ①作業開始前の朝礼の時間、②作業開始前の準備体操の時間、③現場作業終了後の掃除時間 |
| 安全教育などの時間 | 参加することが業務上義務付けられている研修や教育訓練を受講する時間は、労働時間に当たる。 (労働時間となる例) ①新規⼊場者教育の時間、②KYミーティングの時間 |
労働時間の管理を従業員の自己申告に頼る場合、客観的なデータを活用した管理体制を整えることが重要です。これにより、労働時間の把握が可能となり、不適切な給与支払いリスクを軽減することに繋がります。
客観的なデータ収集にはMIMAMO DRIVEがおすすめ
東京海上スマートモビリティが提供する「MIMAMO DRIVE」(社用車の動態管理サービス)を導入することで、車両の走行履歴を記録し、従業員の行動を客観的に確認することができます。GPSデータを活用することで、直行直帰する従業員の状況をリアルタイムで把握し、申告との整合性を確認可能です。
MIMAMO DRIVEの活用方法
労働時間を自己申告に頼る場合の企業が講ずべき措置に対して、車両を必要とする仕事内容におにては以下のようにお役立ていただくことができます。
自己申告制の場合に企業が講ずべき措置
| 1 | 実態を正しく記録・適正に自己申告することを対象者に十分説明 | 客観データ(走行履歴)を自動で記録し、企業側がいつでも事実確認できる環境を整えることで、適切な記録・申告・管理の意識向上に繋がる。 |
|---|---|---|
| 2 | 実際に労働時間を管理する者にも⼗分説明 | |
| 3 | 把握時間と実際の時間が合致しているか、必要に応じ実態調査を実施・補正(社内にいたデータと著しい乖離の場合は実施) | 実態調査を進めるためには、打刻データ(始業就業時刻)からだけでは困難である。従業員への聞き取り調査で、どこで何をしていたのかの深掘りをするために、GPSによる位置情報や車の状態(走行中、停車中)などの活用が可能。 |
| 4 | 申告を超える在社理由を報告させる場合、報告が適正かを確認 | |
| 5 | 申告できる時間数の上限設定や上限を超える申告を認めないなどの、適正な申告を阻害する 措置を講じないこと | 従業員の走行履歴を残すことで、企業として管理者の不適切な管理を防止することができる。 |
また、MIMAMO DRIVEは運転日報の自動作成、アルコールチェックの記録、安全運転診断などの機能も備えており、社用車を利用する建設業にとって業務効率化を図る上で非常に有用です。労務管理の効率化に加え、法令対応、安全管理の向上にも貢献し、企業のリスク低減に寄与します。
- MIMAMO DRIVE 資料紹介
-


MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。
まとめ
建設業の労務管理は、現場分散や自己申告のリスクを抱えています。適切な勤怠管理システムの導入や自己申告の適正化によって、これらの課題を解決し、企業のリスクを軽減することができます。